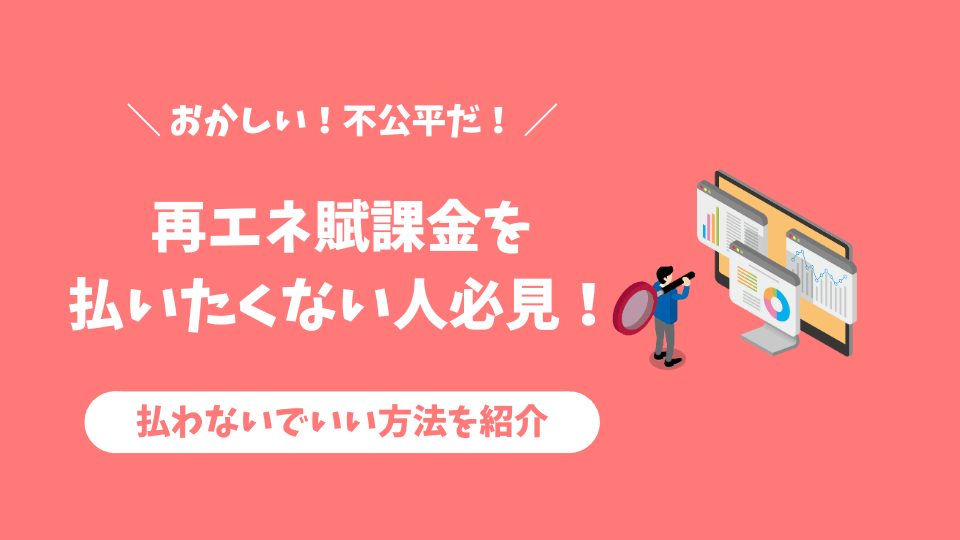再生エネルギー発電賦課金のことを知ってしまった人は、このように思うのではないでしょうか。
- 再エネ発電賦課金は払いたくない!
- 再エネ賦課金の制度はおかしい!
- 払わない方法はあるの?
世界情勢や円安の影響で電気料金の値上がりが続くなか、再エネ賦課金が注目を集めています。
再エネ賦課金は、電気代に勝手に上乗せされていると感じる人も多く「不公平な負担の一つ」と言われています。
再エネ賦課金は、電力会社から買電している人は必ず支払う負担金です。
再エネ賦課金について詳しく説明を受けた人は少なく、気づいたら「毎月支払わされていた」という人が多いのではないでしょうか。
そこで今回、不公平な再エネ賦課金について、詳しく解説した記事を作成しました。
この記事を読めば、再エネ賦課金を深くまで理解でき、自分でできる対策がわかります。
「再エネ賦課金を詳しく知りたい」・「再エネ賦課金を支払いたくない」このような人には役立つ内容なので、さいごまでお付き合いください。
結論として、再エネ賦課金の支払いから逃れる方法は、2つしかありません。
- 自宅で発電して電力会社から買電しない!(太陽光発電)
- 節電を頑張って再エネ賦課金の支払う金額を減らす
私も再エネ賦課金を払いたくないので、太陽光発電を導入して、節電にも取り組んでいます。
おかげで支払う再エネ賦課金は一ヶ月あたり数十円に抑えられています。
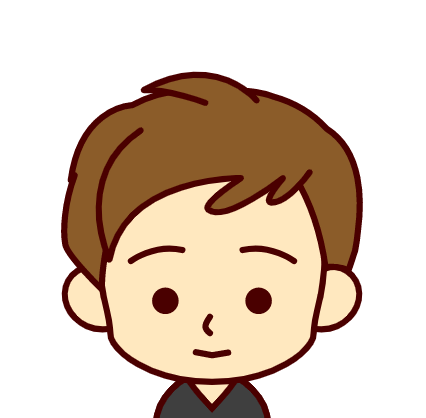
とーや
節約ブロガー|中京圏在住|5人家族の主|
- 家庭での節約について発信中!
- 太陽光+蓄電池を導入!
- 水道光熱費は年8万円以上節約!
- 住宅ローンも最低金利で契約!
私は「節約が好き」な節約人間ではなく、毎月同じ生活なら少しでも得なほうが良い!という考えからさまざまな節約法に関心をもってチャレンジしています。
結論:再エネ賦課金を払いたくない人がやれることは2つ!
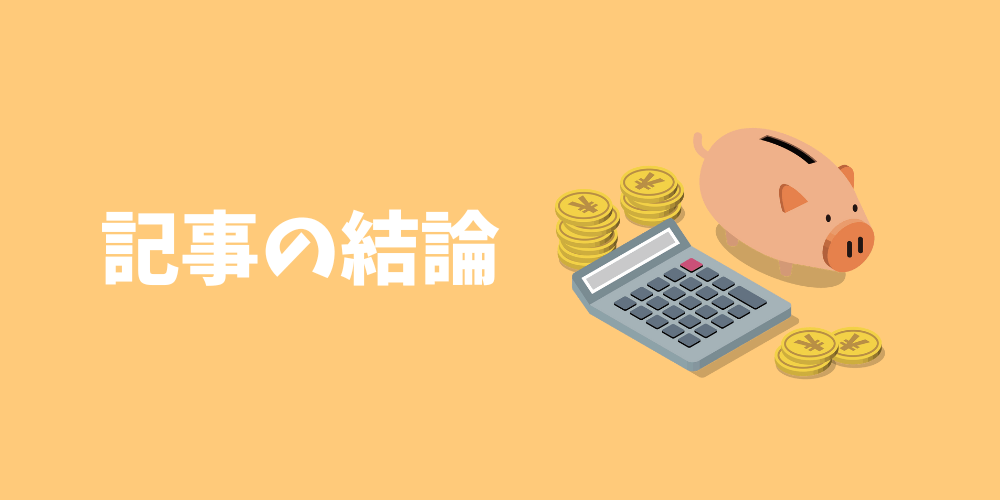
結論として、再エネ賦課金を支払わないためにやれることは2つだけです。
- 自宅で発電して電力会社から買電しない!(太陽光発電)
- 節電を頑張って再エネ賦課金の支払う金額を減らす!
再エネ賦課金の制度については、個人ではどうすることもできません。
頑張っても再エネ賦課金を無くすことはできないので、できるだけ支払わないための対策を実行するしかありません。
私も再エネ賦課金を支払わないために、太陽光発電を導入し、節電にも取り組んでいます。
この記事では、「再エネ賦課金の制度」から順を追って解説していきます。
私が行っている具体的な対策を先に知りたい人は、下記のリンクからジャンプできます。
再生エネルギー発電促進賦課金を略して「再エネ賦課金」
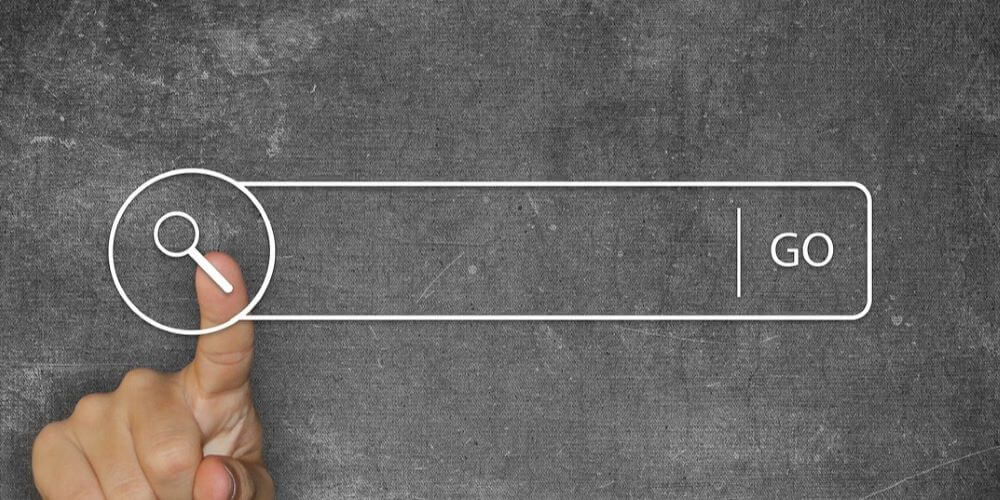
再エネ賦課金は略称で、正式には「再生エネルギー発電促進賦課金」といいます。
いくつかの制度が関連して再エネ賦課金制度を動かしています。
2012年度から再エネ賦課金がスタート
再エネ賦課金は、電気利用者(消費者)が電気使用量に応じて負担する制度で2012年度に導入されました。
国は、2011年3月の東日本大震災をうけてエネルギー政策の大転換を考え再生可能エネルギー(自然エネルギー)の普及を推進しています。
制度の目的は「再生可能エネルギーの発電を普及させること」で、再生可能エネルギーの発電コストを日本国民で広く負担するという内容です。
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど
再エネ賦課金とFIT制度(固定価格買取制度)
再エネ賦課金は、FIT制度(固定価格買取制度)と密接に関係しています。
FIT制度(固定価格買取制度)では、再生可能エネルギーを用いて発電した電気を「一定期間・一定価格」で買い取ることを大手電力会社に義務づけています。
たとえば、2012年度に太陽光発電を設置した家庭の場合、10年間は「1kWhあたり42円」で電力会社が買い取ってくれます。
電力会社が買い取る価格は割高に設定されており、発電した人に支払う金額の一部を再エネ賦課金として消費者が負担しています。
再生可能エネルギーを普及するために必要なコストを、私たち消費者が負担しています。
再エネ賦課金はどの電力会社でも同額
再エネ賦課金は、電力会社によって金額は変わりません。※全国で一律の金額
全国で統一した負担金にすることで、不満や不公平感が出ないようにしています。
したがって、再エネ賦課金を減らすために電力会社を乗り換えても効果はありません。
再エネ賦課金は電気使用量に応じて支払う
再エネ賦課金は、電力使用量に応じて支払うため、たくさん電気を使えば負担する金額が大きくなります。
支払う再エネ賦課金は、賦課金単価に電気使用量(kWh)を乗じて計算します。
再エネ賦課金 = 再エネ賦課金単価 × 電量使用量(kWh)
たとえば、2024年5月~2025年4月の再エネ賦課金単価3.49円/kWhで計算すると、
再エネ賦課金 = 3.49円/kWh × 260kWh = 907円/月
支払う再エネ賦課金は、一ヶ月で907円、年間では10,884円になります。
標準的なモデル家庭で年1万円の負担があり、来年度以降も再エネ賦課金は値上がりすることが予測されています。
再エネ賦課金を支払わない家庭がある
再エネ賦課金は、電気を使用する家庭は強制的に徴収されますが、支払っていない家庭も存在します。
自宅に設置した太陽光パネルで発電した電気を使用している場合は、再エネ賦課金は支払わなくて大丈夫です。
しかし太陽パネルを設置している家庭でも、太陽光で発電した電気以外に電力会社から買電する分に対しては再エネ賦課金を支払います。
我が家も太陽光発電を設置していますが、わずかですが再エネ賦課金を支払っています。
【払いたくない】再エネ賦課金は12年で最大15.7倍まで上昇!

再エネ賦課金は2012年度にスタートし2023年度で12年目になります。
毎年値上げを繰り返していき、初年度の再エネ賦課金と比べて、最大で15.7倍になっています。
制度当初の負担は小さかったのですが、今はとても大きな負担になっています。
【再エネ賦課金】現在までの推移(2012年~2024年)
再エネ賦課金は、年度ごとに単価が改定されます。
制度開始時の2012年度は0.22円/kWhでしたが、13年目の2024年度は3.49円/kWnまで値上がりしています。
0.22円/kWh→3.49円/kWhで13年間で15.9倍です!
制度開始~2024年までの推移
| 単価 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2024年度 | 3.49円 / kWh | 2.49倍 |
| 2023年度 | 1.40円 / kWh | 0.41倍 |
| 2022年度 | 3.45円 / kWh | 1.03倍 |
| 2021年度 | 3.36円 / kWh | 1.13倍 |
| 2020年度 | 2.98円 / kWh | 1.01倍 |
| 2019年度 | 2.95円 / kWh | 1.02倍 |
| 2018年度 | 2.90円 / kWh | 1.10倍 |
| 2017年度 | 2.64円 / kWh | 1.17倍 |
| 2016年度 | 2.25円 / kWh | 1.42倍 |
| 2015年度 | 1.58円 / kWh | 2.11倍 |
| 2014年度 | 0.75円 / kWh | 2.14倍 |
| 2013年度 | 0.35円 / kWh | 1.59倍 |
| 2012年度 | 0.22円 / kWh | – |
標準世帯で年1万円を超える負担額になっている
再エネ賦課金は電力使用量に応じて負担する金額を計算します。
- 2012年
-
月あたり57.2円(年あたり686円)
- 2024年
-
月あたり907円(年あたり10,884円)
13年前には年686円と気にならないくらい小さかった負担額が、現在は年1万円を超える金額になっています。
【おかしい】再エネ賦課金は今後10年間値上がり続ける!

制度当初の2012年から13年間で大きく値上がりした再エネ賦課金ですが、今後はどうなるのか?公的機関が予測した結果を紹介します。
公的機関の予測なので信憑性が高いです!
2032年まで再エネ賦課金は値上がり!
「一般財団法人 電力中央研究所」が2015年に発表した資料によると、再エネ賦課金の値上がりは2032年まで続くと予測しています。
再エネ賦課金は2032年度に4.72円/kWhまで上昇!
引用:一般財団法人 電力中央研究所
再エネ賦課金の予測根拠として、FIT制度の契約数や買取価格などから総合的に算出しています。
予測では2032年をピークにゆるやかに値下がりします!
2050年に再エネ賦課金は0円になる
「一般財団法人 電力中央研究所」の同じ資料によると、2032年をピークに徐々に値下がりし2050年頃まで続くと予測しています。
FIT制度が継続する前提の予測ですが、これから30年間は再エネ賦課金を支払うことになります。
当初の予測よりも大幅に値上がりしている
環境省は2013年に再エネ賦課金の推移を予測していますが、現在の再エネ賦課金は予測よりも大幅に高い金額になっています。
今後の予測として2030年がピークで最大2.95円/kWhになると予測。
引用:環境省
環境省の予測では2030年に最大で2.95円/kWhですが、実際の再エネ賦課金は2019年度に2.95円/kWhに達しています。
想定を超えて再生エネルギーが普及した結果、再エネ賦課金が高くなり電気料金を支払う消費者の負担が大きくなっています。
再エネ賦課金に対する世間のイメージ

再エネ賦課金に対して悪いイメージをもっている人はたくさんいます。
制度導入から12年経過しましたが、ここ数年でネガティブな声が大きくなっています。
制度当初は年間の負担額も数百円だったので気にならなかったが、現在は年1万円を超える負担になっているため多くの人が意識するようになっています。
この記事では、ネガティブな声や意見を紹介します。
再エネ賦課金は不公平な制度
一般消費者が支払った再エネ賦課金を太陽光パネルを設置している人が貰う不公平な制度だと思う
再エネ賦課金は電力会社が徴収しますが電力会社の儲けにはならず、太陽光発電などで余剰電力を売電している人に支払われます。
再生可能エネルギー普及のために、一般消費者から集めた再エネ賦課金で「割高な買取価格を補っている」と考えると不公平な制度と感じてしまいます。
残念ですが、不公平な制度から逃れることはできません。
再エネ賦課金はおかしい制度
再生エネルギーの普及を進めるために国民に大きな負担を強いる制度はおかしい!
自国内でエネルギーの消費率を高めるための政策として自然エネルギーを推進することは間違っていないが、負担を国民だけに強いるのはおかしいと感じている人も多くいます。
制度当初の少額な負担から年1万円を超える負担になったことで、多くの人が問題として認識しています。
【払いたくない】再エネ賦課金から逃れる方法

結論として、再エネ賦課金の支払いから逃れる方法はありません。
どれだけ「再エネ賦課金を払いたくない」と思っても0円にすることはできません。
あなたができることは、「再エネ賦課金の支払う金額を減らすこと」か「再エネ賦課金の支払い以上にお得に生活すること」のどちらかです。
この記事では、再エネ賦課金の支払額を減らす2つの対策法と、再エネ賦課金の支払い以上にお得に生活できる方法を紹介します。
- 太陽光パネルを導入して電気を自給自足する!
- 節電を頑張って支払う再エネ賦課金を減らす!
- 安い電力会社に乗り換えて再エネ賦課金の支払い以上に得する!
【再エネ賦課金の対策】太陽光発電を導入する!
自宅に太陽光発電システムを設置すれば、再エネ賦課金の支払額を極力無くすことができます。
私は、2023年5月に太陽光パネルと蓄電池を導入して電気を自給自足しながら生活しています。
おかげで、支払っている再エネ賦課金は一ヶ月あたり数十円です。
我が家の太陽光ライフについては、関連記事で詳しく紹介しているので興味がある人は読んでみてください。
しかし、太陽光発電は戸建て住宅しか設置できないので、すべての人ができる対策ではありません。おすすめは次の対策法です。
【再エネ賦課金の対策】節電する!
節電を頑張って電気を使う量を減らせば、支払う再エネ賦課金を減らすことができます。
再エネ賦課金は電力使用量に応じて支払うため、使用量を減らせば再エネ賦課金も減ります。
特に、夏や冬は冷暖房など電気を使う時間が増えるので、使用量が多くなります。
節電すれば、再エネ賦課金だけでなく電気代自体も安くなるのでおすすめです。
しかし、節電に取り組む人のなかには、間違った方法や効果の低い方法を頑張ってしまう人がいます。
間違った方法で節約をしてしまうと、効果が得られないだけでなくトラブルを引き起こしてしまうかもしれません。
家庭でできる正しい節電の方法は、下記の記事で解説しています。頑張って節電したい人にオススメな内容なので読んでみてください。
【再エネ賦課金の対策】お得な電力会社を乗り換える!
再エネ賦課金の支払いを減らすといっても限界があります。
どんなに節電を頑張っても「一ヶ月あたり数百円」減らせれば上出来でしょう。
再エネ賦課金を減らすことが難しいなら、再エネ賦課金の支払い以上にお得に生活することを考えてみませんか?
お得に生活する方法はいくつかありますが、簡単にできる方法として「電力会社の乗り換え」がおすすめです。
電力会社を乗り換えれば、年間で2万円~8万円も電気代が安くなります。
再エネ賦課金を年間1万円支払ったとしても、それ以上にお得です。
しかし、電力会社の料金プランは複雑で「どの電力会社に乗り換えたほうが良いのか判断できない…」という人がたくさんいます。
私はたくさんの電力会社を比べてきましたが、なかでも「Looopでんき」がおすすめです。
Looopでんきなら、
- 大手電力会社よりも年間で最大8万円も安くなる!
- 電気の使い方を工夫すればさらに安くなる!
- スマホでリアルタイムに電気料金が確認できる!
さまざまなメリットがあるので、電気代を節約したいと考えている人におすすめの電力会社です。
\ 最大8万円も電気代が安くなる! /
最短5分!すぐに乗り換えれる!
Looopでんきを詳しく知って納得して申し込みたい人には、特徴やデメリットを解説した記事がおすすめです。
まとめ:再エネ賦課金を払いたくないなら節電しよう!
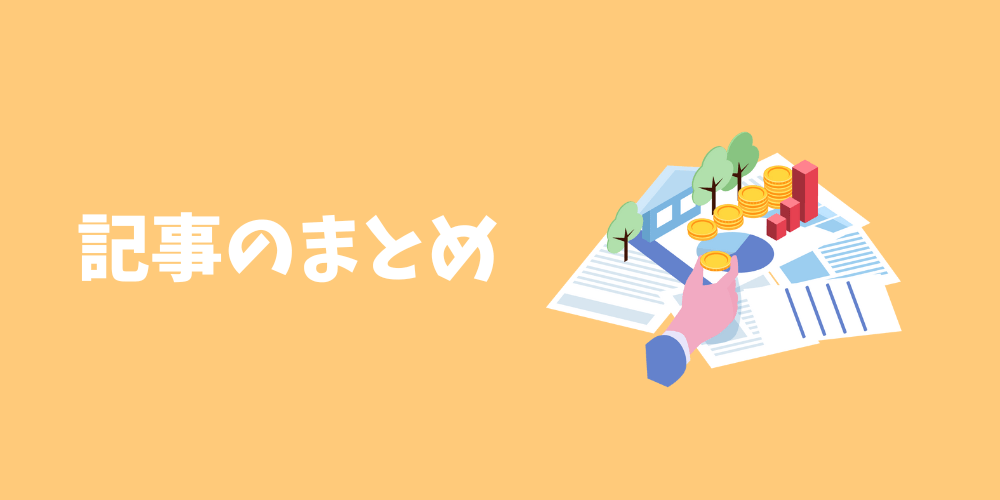
この記事では、再エネ賦課金を払いたくない人のために対策法について解説しました。
- 再エネ賦課金は2050年まで支払うことになる!
- 再エネ賦課金の支払いから逃れることは難しい!
- 支払わないことよりも減らすことを考えよう!
- 再エネ賦課金よりも他の支出を減らすほうがカンタン!
再エネ賦課金の支払いから逃れることはできないので、「支払いを減らすこと」か「他の支出に目を向けること」がおすすめです。
誰でも、すぐにできる対策として、2つ紹介します。
- 節電を頑張って支払う再エネ賦課金を減らす!
- 安い電力会社に乗り換えて再エネ賦課金の支払い以上に得する!
節電して電力使用量を減らせば、再エネ賦課金の支払う金額も減らすことができます。
しかし、節電に取り組んでいる人のなかには、間違った方法や効果の低い方法を頑張っている人もいます。
間違った方法で節電してしまうと、効果が得られないだけでなく、トラブルを引き起こす可能性があります。
正しい節電の方法については、関連記事で紹介しているので参考にしてください。
個人的には、節電を頑張るよりも、大きく節約できる「他の支出に目を向ける」ほうが効率が良いと考えています。
たとえば、電気代の節約でいえば、電力会社の乗り換えです。今よりもお得な電力会社に乗り換えれば年間で2万円~8万円も電気代が安くなります。
私のおすすめの電力会社は、「Looopでんき」です。
Looopでんきなら、
- 大手電力会社よりも年間で最大8万円も安くなる!
- 電気の使い方を工夫すればさらに安くなる!
- スマホでリアルタイムに電気料金が確認できる!
さまざまなメリットがあるので、電気代を節約したいと考えている人におすすめです。
\ 最大8万円も電気代が安くなる! /
最短5分!すぐに乗り換えれる!
Looopでんきを詳しく知って納得して申し込みたい人には、特徴やデメリットを解説した記事がおすすめです。